「投資を始めよう」と思って、まず最初にイメージしたのは株式投資です。1年ほど前から国内の株式投資を始めましたがその間の試行錯誤の歴史を紹介します。
株式投資に興味を持ち始めた方に、参考になれば嬉しいです。
キャピタルゲインを狙うのは困難
株式投資で利益を得ようとする場合、その手法は大きく分けて2種類あります。
- キャピタルゲイン:保有株式を取得価格より高値で売却することで利益を得る
- インカムゲイン:株式を保有することで利益を得る(配当金)
株式投資を始めた当初は、安い時に買って高い時に売る所謂「キャピタルゲイン」の印象が強く、自分なりに上がりそうな株を選んで購入していました。しかし結果は全くうまくいきませんでした。
銘柄選びが難しい
もちろんですが、「株価が上がりそうな会社の株を買う」ことはとても難しいです。
これまでであれば、例えばユニクロを展開する「ファーストリテイリング」、パーソナルジムの「RIZAP」、最近だとアメリカの電気自動車会社「テスラ」でしょうか。
今考えればこれらの会社の株式を安いときに買っておけばと誰しも思いますが、事業が成功して株価が急騰する会社でもまだ株価が安いときには
- まだ有名ではなく誰も知らない会社
- 将来性がまったく分からない会社
- 起ち上げたばかりで財務状態が悪い会社
なわけで、そのときにリスクを承知で株を買うためには、相当な情報力と勇気が必要であり、僕にはありません。
日中は値動きのチェックができない
キャピタルゲインを得ようとすると、株価の推移をある程度リアルタイムで追う必要があります。目星をつけた会社の株式を買うとき、売却するタイミングを計るとき、日中の株価が気になりますが、サラリーマンには昼間にそんな余裕はありません。
時々スマホでチェックすることはできますが、ずっと証券会社のアプリを見続けることは無理です。したがって、市場が始まる前に発注を済ませておくなどするしか手がありません。
株価の予測が難しい
一般的に株価が上下するタイミングとしては以下のとおりです。
- 年4回の決算発表日
- 業績予想の発表日
- 配当金の権利確定日
その他、為替変動、政治情勢、NY等の株式市場の影響を受けます。これらを総合的に考慮して、長期的・短期的に下落するのか・高騰するのか、的確に判断することは非常に難しいです。
コロナ影響で株価は下がったとき、僕はまだ2番底があると判断して買うことをためらってしまいましたが、その後すぐに株価は上がってしまいました。あのとき買っておけば、と思ってももう遅いです。
高配当株への投資に至った理由
サラリーマン投資家にはインカムゲイン投資が合う
キャピタルゲインを狙った投資を試して試行錯誤した結果、うまくいかなかったこともあり、配当金収入を得るインカムゲインの方に興味が移っていきました。
インカムゲインは、キャピタルゲインと比べて大きく儲けられる可能性はないですが、大きなメリットがあります。
値動きを注視しなくて良い
多少株価に変動があっても配当金目的であればすぐには売却しませんから、日中ずっと株価チェックをする必要はありません。
株式売却を考えるのは、配当金が著しく下がった場合などに限られますので、後で述べますが累進配当政策を掲げる会社の株式であれば、減配のリスクを低く抑えることができます。
収入が予想しやすい
例えば日本たばこ産業(JT)の2019年度の1株当たり配当金は154円でした。いま僕はJT株式を600株保有していますので、年間で92,400円の配当金が得られる計算です(正確には20%程度の所得税が差し引かれますが)。
JTは2020年度についても1株当たり配当金予想を154円としていますので、今のところは前年度と同額の配当金が得られることになります。
このように、配当金額は会社が毎年決定しています。もちろん業績が悪化した場合、減配あるいは無配に陥る可能性もありますが、いくら投資していくら利益を得られるか計算がし易いことが特徴です。
高配当銘柄とは
高配当銘柄を選ぶにあたって、ポイントとなる項目は以下のとおりです。
配当利回り
例えば、僕が所有するJT株式の配当利回りは、平均取得価格(1株当たり)が2,126円、JTが公表している2020年度の配当予想は中間配当と期末配当合計して154円(1株当たり)なので、154÷2,126=7.2%となります。
1株当たり配当金が高いほど、株価が安いほど、配当利回りは高くなります。配当利回りの高い株を買う方が、効率的に配当金を得ることができます。
配当性向
JTを例にしますと、2019年度決算の1株当たり純利益195円、2019年度の配当金は1株当たり154円でしたので、154÷195=78.6%となります。
1株当たり配当金が高いほど、1株当たり利益が低いほど、配当性向は高くなります。配当性向が高いほど、利益の中から多くを配当金に回しているという意味になります。
配当性向が高い企業は、株主還元に積極的と判断できる反面、収益力の割に無理して配当している場合もあり翌年度以降に減配のリスクを抱えていると考えることもできます。
企業の配当政策
三菱商事、三井住友フィナンシャルグループは累進配当政策を掲げ、中長期的に配当金を増額することを公表しています。このように配当額を重要視する経営姿勢を示している企業は、減配のリスクが少ないと言え、また増配が期待できます。累進配当を明言するまではしていないものの、花王、JTなどは高配当を継続しており、2020年度に減配を表明しましたが、キヤノンも配当を継続していました。
企業の収益力ももちろん配当の安定性には欠かせませんが、同時に企業それぞれの配当に対する方針も重要となります。
主な高配当株式銘柄
まだ海外の株式には手を出していませんので、国内に限った話になります。もっとたくさんありますが、主要な銘柄は以下のとおりです。
| 配当利回り | 配当性向 | 配当政策 | |
| 三井住友FG | ◎ 6.5% | ◎ 37.0% | ◎ 累進配当政策を掲げる |
| 三菱商事 | ◎ 6.0% | ◎ 37.9% | ◎ 累進配当政策を掲げる |
| JT | ◎ 7.8% | △ 78.6% | 〇 配当⾦の安定的/継続的な成⻑ |
総括
例えば、これから給与・賞与毎年100万円ずつ投資に回しJT株式を買い続けたとします。株価下落リスク、減配・無配リスクを抱えますが、現状の配当利回りが継続されると仮定した場合、2,000万円×7.8%=156万円の不労所得を得ることができます(実際には所得税が20%程引かれます)。
キャピタルゲインを諦めたわけではないですが、配当金によるインカムゲインを手厚くすることを優先する方針とし、上記の三井住友FG、三菱商事、JT株を買い増す方針で当面頑張っていきます。
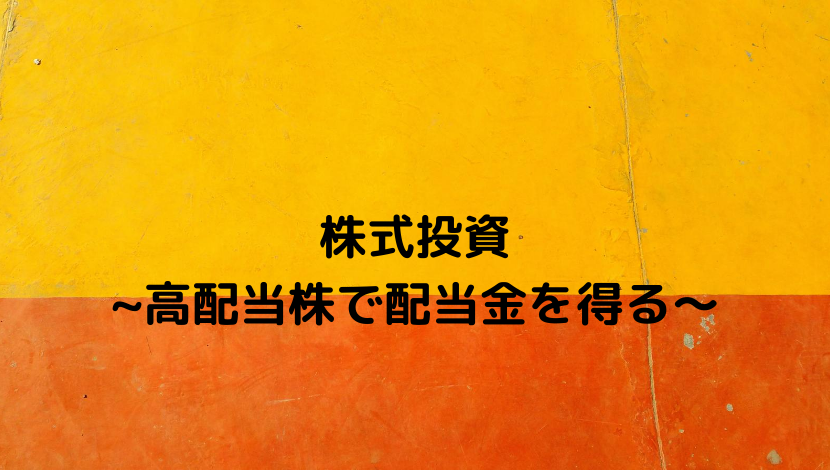
-~土日の都心移動をお得に~-120x68.png)

コメント